
HR/HMの世界に留まってた筆者にロックの無限の可能性を教えてくれたのはBruford氏のドラミングであった。もちろん、HRの世界にもすばらしいドラマーはたくさんいるし、今でもIan PaiceなどはFavorite Drummerの一人だが、Bruford氏のドラミングは一種麻薬、劇薬的な魅力を持つ。最初に聴いても理解不能だが、聴き続けるうちに抜け出せなくなる。気合いが入った時(自分のやりたいことをやっているとき)とはっきり活動資金稼ぎだとわかる手抜き時(時には口に出してしまうことも(苦笑))との落差がすばらしく?激しいのも微笑ましい。
本コーナーは、Bruford氏に敬意を表して設けたものである。2002年4月の来日を記念して、この度いくつかの資料を追加した(肖像権侵害と言われれば弁明の余地はないが)。
星の数ほどあるBruford氏の作品すべてを紹介することはできない(だいたい筆者もすべてを把握しているわけではない)が、特に有名な作品はほとんどすべて並べたつもりなので、本コーナーを読んで氏のドラミングに触れていただければと思う。(しょーもない作品への代打ち的参加、2〜3曲のみのゲスト参加作品もかなりあるのだが、それらの多くはここでは割愛した。)
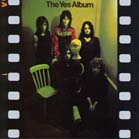
Yesの3作目。ギタリストがSteve Howeに替わり、楽曲も複雑、かつ緻密になった。ここから3枚がYESの黄金期といってよいだろう。この頃のBruford氏のドラミングは正確なメトロノームのようなもので、この後顕著になるど派手な華やかさは、まだそれほどない。しかし、当時から存在感抜群のドラムは注目されていたらしい。
キーボードがRick Wakemanに替わり、いわゆる黄金ラインナップによる最初の作品。バンドでの曲の間に各人のソロを入れるという奇抜な構成ながら、それが見事にはまっている。Bruford氏のドラミングはこのアルバムから、派手さを増しているように思える。もちろん、彼の作品も入っている。「Roundabout」は名曲。

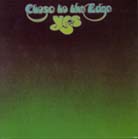
詳細は「おすすめの1枚」のコーナーを参照されたい。とにかく、Bruford氏のドラムはすばらしい。ちなみにSiberian Khatruのリフは、Steve Howeではなく、Bruford氏が作ったものらしい。(1999年のSteve Howeインタビューより)
全盛期のYESを脱退し、あえて空中分解状態だったKING CRIMSONに加入。ジェイミー・ミューアという凄まじいパーカショニストとのツインドラム構成だった。若きBruford氏はここでもメトロノーム役。本人がやりたかった即興的部分はジェイミー・ミューアに持っていかれてしまう形になったが、本作での経験が後のBruford氏に与えた影響は巨大(本人談)。

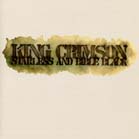
ジェイミー・ミューアが脱退し、メトロノームと即興の両方を独りで担当することになったBruford氏。KING CRIMSONのドラマー=Bill Brufordというイメージは、おそらく本作から。即興的要素の濃い本作のうちの何曲かは、実はライブ録音なのだが、とてもそうは聞こえない。傑作。
一般に有名な曲はないし、難解な曲もあるのだが、Crimsonに入るのならこのアルバムからが最も入りやすいだろう。とにかくヘヴィである。おそらく当時のLed ZeppelinやDeep Purpleよりヘヴィでかつメタリックなサウンドであろう。そういう意味でいわゆるヘヴィメタルのファンも聴きやすいかもしれない。構成と演奏力は完璧で、1曲目のインストから聴くものを圧倒(寄せ付けない?)し、そのままJohn Wetton独特のバラードに流れていく。3曲目はBill Brufordの独壇場だ。

この曲に限らず、ドラマーのアルバムではないかと思われるほど、このアルバムでのBrufordは際だっている。この作品が好きになるかどうかは、彼のドラミングが好きか嫌いかにかかっていると言えるかもしれない。John Wettonのベースはねばり強く腰の太い音を聴かせる。機械のように正確無比なBrufordのドラムとは少々異様な組み合わせなのだが、それがこの時期のCrimsonサウンドを支えていたのである。Robert Frippのギターも相変わらずすばらしいのだが、この二人が打ち出す奇妙なリズムの前には少々分が悪い。筆者はこの作品を聴いて、リズム隊こそがロックを支えているのだと知るに至った。
4曲目は難解なインスト。ほとんど即興演奏であろう。この時期のCrimsonはライブでの即興を重視しており、その姿勢が反映されたものである。ちなみに前作の「Starless And Bible Black」では、ライブでの即興が何曲かアルバム作品として納められているが、解説を読まない限りそれがライブであるとは思わないだろう。
本作の最後を飾るのは、「Starless」。現在でもJohn Wettonがソロライブで取り上げているこの曲は、70年代Crimsonの辞世の句である。前半のバラードから後半の圧倒的演奏まで、全く隙がない。「完璧」なアルバムには滅多に出会えないが、「RED」はその数少ない作品のひとつであると断言できる。彼のドラミングスタイルは、本作で完全に確立されたと言っていいだろう。

Peter Gabriel脱退で頭を抱えていたPhil Collinsに、リードヴォーカルをとるように薦めたのはBruford氏らしい。それにより空いたドラマーの席には、KING CRIMSON分解で暇だったBruford氏が暫定的に座ることに。その後、Chester Thompsonというドラマーが見つかって、Bruford氏は晴れてソロに。本作はその頃のライブ。Bruford氏は2曲で登場。
70年代プログレッシブロックの最後の大傑作。久々に実現したJohn Wettonとのリズムセクションがうれしい。ソロアルバムで親交のあったAllan Holdsworthも参加している。しかし、これだけのメンバーがそろうと意見の対立もやむなし。たった1枚を残して、氏とAllanは脱退。Bruford氏のドラミングは、本作でひとつの頂点を極め、この後はエレクトリックドラムに傾倒していくことになる。再結成の噂があったが、どうなったのだろうか?

70年代中〜80年代中までのBruford氏のソロ作品から選ばれたベスト盤。この時期、Allan HoldsworthやPatrik Morazなどと組んでソロアルバムを出していた。アコースティックからエレクトリックへと興味が変化していく氏の姿が見える。ドラミングのスタイルも、ドラムをリズム楽器としてだけでなく、リード楽器的なものとして解釈し、実験的な要素も強い。
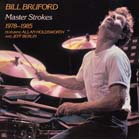
80年代に入り復活したKING CRIMSONは、メンバーにAdrian BlewとTony Levinが加わり、70年代とは全く異なる斬新なロックを展開。変拍子、ポリリズムなどを取り入れた。ここでは、氏のエレクトリックドラムが重要な地位を占めており、Tony Levinとの名コンビもここから始まった。間違いなく80年代大傑作のひとつ。氏のドラミング冴える!
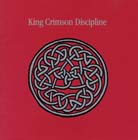

80年代CRIMSONの2作目。前作よりさらにダンスミュージック的要素が強く出ている。もっともCRIMSONで踊れる人はあまりいないと思うが・・・。氏がこういう音楽をやりたかったかどうかわからないが、当時エレクトリックドラムの第一人者だった氏がいなければ、実現できない音楽であったことは間違いない。
80年代CRIMSON三部作の最後。基本的には前2作の延長にあり、Disciplineの時のような斬新さ、驚きはないが、氏は相変わらずの安定したドラミングを披露。ハイライトはタイトル曲と「太陽と戦慄Part3」。

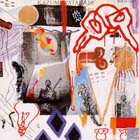
実はBruford氏は、結構日本人のアルバムに参加している。極端なところでは久石譲、杏里(!)などがあるが、この渡辺香津美とのアルバムは本格的なもので、Bassは盟友Jeff Berlinである。この面子で日本国内をツアーしたのだから驚きだ。氏のドラミングは久々にロック向けのスタイル。とはいっても当時の渡辺のギターがRobert Frippの影響をもろに受けており、 CRIMSON的な面も。快作といってよい。
渡辺香津美とのコラボレーション2枚目。前作もそうだったが、氏自らペンをとった曲も収録されている。実は氏が作る曲は意外にもメロディーが美しい。リズム重視の作品かというとそうでもないのである。この傾向は、後のEarthworksで顕著になる。本作は前作よりもさらにストレートな感じであるが、氏独特のドラミングはそれほど表には出てこない。少し手を抜いたか?(笑)
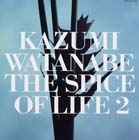
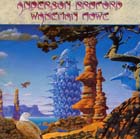
しばらくEarthworksでJazzの世界にいた氏がYESを飛び出したJon Andersonに誘われて、Close to the Edgeの頃のメンバーで作ったのが本作。BassはTony Levin。80年代最後を飾る大傑作。昔のYESと異なり、氏がエレクトリックドラムを叩いているのが特徴。ドラミングはかなりストレート。個人的には、このメンバーでしばらく活動してほしかった。
Anderson, Bruford, Wakeman, Howeのライブ盤。YESの曲を多く演奏している。氏が初めてClose to the Edgeを叩いたことで注目された。残念ながら当日Tony Levinが体調を崩し、Jeff Berlinが代役でBassを弾いている。90年来日時はTony Levinだった。筆者が氏の生演奏を初めて観たのが、この時。ドラムセットはこの頃が最大・最高価。そのあまりの複雑さ、凝り様に、さすがに本人も「我ながら阿呆ではないか」と思ったそうだ(笑)。
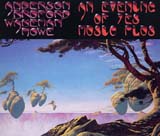
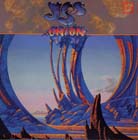
Jon Andersonの暴走に振り回される形で新旧8人のメンバーが集まったYES名義の作品。しかし、内実はAnderson, Bruford, Wakeman, Howeの2ndと80年代YESの新作からの曲をごちゃまぜにしたもの。散漫な感じは否めない。しかし!ABWHだけの曲を集めると、ちょうど46分。大傑作になる。やはり、純粋にABWHとして聴きたかった。氏とTony Levinのコンビネーションは抜群。ライブではAlan Whiteの遠慮のないドラムにかき消されて、氏の音はあまり目立たなかった。氏は相当ご不満の様子だった。このあと、YESを予想通り再脱退。
VJCP-28071 1991年
本作以前のEarthworksの音作りは、どちらかというと氏のドラミングが全面に出ていて、ドラムの実験作というイメージが強かったが、本作はバンドの作品として非常によく作られている。曲もよく、ひとつの到達点といえる。
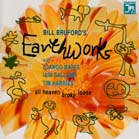

YES時代の盟友Steve Howeのソロアルバム。実は前述YESの「Union」に収録されている曲のうち、数曲の元ネタが本作に含まれている。つまりは、ABWH時代にHoweが作った曲ということだ。その関係で、氏がその大半でドラムを叩いている。氏のドラミングは ABWH的(当然だが)。Howeはいまだに氏がYESに復帰することを熱望しているらしいが、その理由は氏独特の感性にあるらしい。
1973年〜74年までのCrimsonライブ音源をデジタルリマスターし、CD4枚組として出されたボックスセット。すでにジェイミー・ミューアは脱退した後で、氏のドラムが強烈にフィーチャーされている。氏が叩く「21世紀の精神異常者」など、これまで海賊版でしか聴けなかったもので、貴重な音源だ。しかし、さすがにCrimsonのライブを4枚立て続けに聴くというのは、体力的にも精神的にも厳しい(苦笑)。とはいえ、厳選された音源だけあって、演奏内容もすばらしい。限定発売だったので、もし中古屋などで見つけたら、即買うべし。

旧メンバー時代のEarthworks唯一のライブ音源。選曲もベスト的性格が強く、聴きごたえがある。U.K.後模索していたスタイルであるエレクトリックドラム時代の最後を飾る素晴らしい内容。氏の精進15年の集大成。
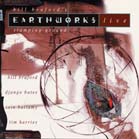
90年代Crimson始動期に発表されたミニアルバム。ドラム二人、ベース二人、ギター二人の構成。氏のドラムはアコースティック中心に移行している(録音時はTAMAのアートスターキット。直後からスタークラシック)。数枚のエレクトリック(シモンズ)も使っているが、おかず的な使い方である。しかし、二人ドラムがいながら、圧倒的な氏の存在感に驚かされる。名盤。


VROOOM発売後、アルゼンチンで行ったライブを収録。Crimsonというバンドは、元々ライブを重ねることによって出てきたアイデアをスタジオに持ち込んでいたのだが、本作もフルアルバム制作を視野に入れたものであった。ここでは、まだ進化途中の6人編成Crimsonのサウンドが聴ける。氏のドラミングの存在感は相変わらずすさまじい。
90年代Crimsonの最初のフルアルバムは、今のところ氏にとっては最後のCrimson参加作品となってしまっている。ツインドラムの音はVROOOMより随分整理され、VROOOMの時に感じられた途方もないエネルギーはないものの、しっかり構築されたアルバムである。ライブだとここまでこぎれいな音ではないのだが。氏のドラミングも無難な印象。このあたりから、当時のバンドのあり方に懐疑的だったのではないだろうか?

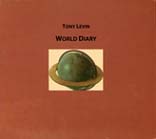
Crimsonの盟友、Tony Levin初のソロアルバム。氏は2曲のみの参加。ここではエレクトリックドラムのみを叩いているが、これはTony Levinからの要請か?特に「Jewel」は、YES「Union」の「Even Song」の続編のような作品。美しい「メロディ」を氏がドラムで奏でる。
King Crimsonの新作の中で、即興的色合いの濃い「Thrak」のインプロビゼーション部だけを集めた恐るべき(笑)マニア向けライブアルバム。こういった即興では氏の力量がいかんなく発揮される。はっきり言って独壇場だ。Tony Levinとのコンビネーションは、Robert FrippとAdrian Belewをすっかり食っている。氏とTonyが好きな人は買い。
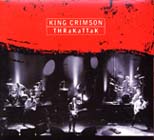
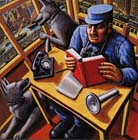
70年代Crimsonのライブ音源がデジタルリマスターされて発売された。もはや何も言うことはない。最高である。筆者が一番好きなCrimsonは、やはりこの時期である。その思い入れがあまりにも強いため、公平な評価ができない(苦笑)。が、氏に言わせれば、この頃は皆若くて、この当時としては「うまくやっているつもりだった」らしい。氏らしい厳しいコメントではある。
思い出したように発売された旧メンバー時代のEarthworksベスト。筆者はこの時点でEartheworksは解散したものと思っていた(事実、それに近いものだったのだが)。Earthworksのエッセンスをてっとりばやく体験するにはうってつけ。
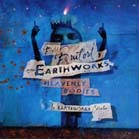

氏がアコースティックなジャズにのめり込んでいく過程に発表された純粋ジャズ作品。Eddie Gomez、Ralph Townerともその道では非常に有名なベテランミュージシャン。ジャズの世界では氏より格上である。そういった点から見ても、氏のジャズへの傾倒が本気であることがわかる。そのドラミングも本格的ですばらしい。失礼な話だが、正直ここまで叩けるとは思わなかった。
Tony Levin(b)、Chris Botti(trumpet)、David Torn(g)と氏が組んだグループ。Crimsonのプロジェクトシリーズと同時期に活動していたもので、来日公演はプロジェクト2とジョイントだった。実はプロジェクト2よりこちらの方が圧倒的に盛り上がっていたのだ。氏も実に楽しそうにドラムを叩いていたのが印象的であった。アルバムの内容は、やや前衛的なフュージョン系ロックといったところか。Led Zeppelinの曲をパロったと思しき曲もあり、けっこう楽しめる。が、マニア向けだろう。
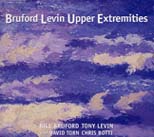
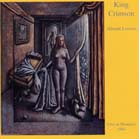
Robert Frippの商才が見事に発揮されている旧音源ライブ盤突如発売シリーズのうちの1枚。これは80年代Crimsonのライブ。しかも2枚組。エレクトリック時代の氏のドラミングを堪能できる。かなりいい内容だ。こうして聴くと、80年代Crimsonはいいバンドだったのだと、つくづく思う。
90年代Crimsonは「Thrak」以降、次に進むべき道がなかなか定まらず、暗中模索状態だった。アイデアを見つけるためにFrippが始めたのが、メンバー6人をいろいろ組み合わせて実験作を作るという「ProjeKct」シリーズだ。本作は氏、Levin、Fripp、Gunnが行った完全即興ライブの模様を収めたもの。こういうライブは氏はお手の物である。久々にFrippも「本気で?」弾いており、激しいライブになっている。これをCrimson名義で出してもよかったのでは?本作を最後に氏はCrimsonと訣別。


DGM-9905 1999
Earthworksは、元々エレクトリックドラムの可能性を模索するために、実験色の強い現代ジャズを展開していたのだが、本作で聴くことができるのは、アコースティックなジャズである。エレクトリックドラムは排除されている。
90年代後半になり、エレクトリックドラムによる表現の限界を感じたBillがアコースティック志向に回帰したことが、Earthworks変貌の原因である。(皮肉にも90年代後半はRolandやYAMAHAなどの日本メーカーが続々と新しいエレクトリックドラムを開発し、King CrimsonのRobert Frippはその可能性に興味を示した。Crimsonの新作はほぼすべてがRolandのV-drumを使ったものだ。この方向性の違いが両者を訣別させることになる。)
本作では、Billの長年の夢であった本格的なジャズを堪能することができる。メンバーは英国の腕利きを集め、ブリティッシュジャズの底力を見せつけられる。とはいえ、そこは少し癖のあるBillのこと、しっかり変拍子を全面にちりばめており、曲に適度な緊張感を持たせている。通常ジャズではこのような変拍子はあまり使われないのだが、しっかりついてくるメンバーもたいしたものである。
1曲目はとにかくすばらしい。この曲を聴くためだけに2500円払っても惜しくないくらいだ。学生の時にこの曲を聴いていたら、筆者はジャズの道をばく進したに違いない。名曲中の名曲といっていいだろう。もちろん、他の曲も充実している。捨て曲はない。美しいバラードも収録されている。そして、これらの曲の大半(6曲目と8曲目以外)は、Bill自身が作曲しているのだ(メンバーとの共作も含む)。彼のソングライティング能力は相当なものである。
BillのドラミングはElvin JonesやBuddy Richのように「何でもこなす天才的」なものではないが、ツボを得た心地よいものだ。Patrik Claharのサックスは美しくメロディを奏でる。このバンドの中で唯一エレクトリックなサウンドはSteve Hamiltonのキーボードだが、それも耳障りにならないようアレンジされている。当然アコースティックなピアノも聴かせてくれる。ベースのMark Hodgsonは、あまり目立たないのだが、バンドの屋台骨として、サウンドをしっかり支えている。
氏がおそらく最終目的地としていた本格ジャズの世界がここにある。もはや、氏をジャズドラマーと言っても誰も異論を挟む者はいないだろう。プログレの世界で戦ってきた氏の安らぎの地がここにある。
PCCY-01435 1999
このバンドは意外にも長期的な活動となった。世界規模のツアーも敢行し、日本にも来た(当然、筆者も見に行った)。上機嫌でドラムを叩く氏の姿が印象的だった。David Tornのギターも変則的だがおもしろい。かなり高度なアンサンブルを聴かせてくれる興味深いライブアルバム。なお、Tony Levinのまめな日記調手記もついていて、楽しい。
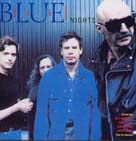

2000
コレクターアイテムとして、ファンクラブ会員のみ通信販売されていた80年代ライブ音源が、日本では限定だが一般販売された。ジャケット写真に写った氏とTony Levinの若いこと・・・(特にTonyは額にしわがない!)ライブの内容はさすがに良好。氏のエレクトリックドラムが妙に懐かしい。
上記82年ライブとカップリングで、日本では限定発売された95年のライブ。「B'boom」と比べると、アンサンブル、音のバランス、役割が随分変わっていることがわかる。氏がCrimsonとしてクレジットされた最後の作品となってしまった。Tony Levinとともに氏がバンドの華だったことを再認識できる作品。
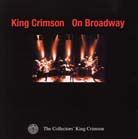
PCCY-01496 2001
2001年2月、来日直前に発売された傑作。前作では一部にシンセサイザーが導入されていたが、本作はフルアコースティック。随所にBruford節(全編氏の作曲)が聴かれ、リズムも非常に複雑である。それでいて聴きやすいのはさすが。新生Earthworksの方向性が本作で確立された。前作とともに必聴盤だ。
PCCY-01394-3 2001
Jamie Muir在籍時の貴重な音源がマニア向けに発売されている。モノラル録音ながら迫力は満点。氏曰く、この頃のCrimsonでは、Jamieが好き勝手叩く悪役(KISSよりも何年も早く、演奏中に血を吐いたりしていた)で、氏は「いい子役」だったとのこと。
PCCY-01493-1 2001
以前より海賊盤で出回っていた70年代Crimsonのラストライブ。MCで「これが最後だ」と言っているあたり涙を誘う。が、内容はそのあたりの情を微塵も感じさせない完璧なもの。この後20数年間演奏されなかった「21st Century Schizoid Man」を聴くことができる。Crimsonファンならマストアイテム。
PCCY-01493-2 2001
80年代Crimsonは、実は「Discipline」というバンド名で始まった。この音源はその幕開けともいえるライブ。非常に小さなライブハウスでのものだ。口コミで集まった大勢のファンの熱気が伝わってくる。そして、このライブでは氏はアコースティックドラムを使っている。おそらく氏が「Red」を演奏したのはこの時が初めてではないだろうか?いろいろな意味で貴重な音源だ。なお、録音状態はめちゃくちゃである(苦笑)。
PCCY-01539-2 2001
70年代Crimsonがまさに空中分解直前の鬼気迫るライブ。氏のドラミングには何かに取り憑かれたような激しさと鋭さがある。ラストの「Easy Money」はまさに完璧。Crimsonの名演の一つに挙げてよいのではないだろうか。とにかく74年の彼らの演奏はすばらしい。このマニア向けシリーズではまだ2枚しか出されていないが、もっと出してほしいものだ。こういうのを聴くと、氏にCrimsonに戻ってほしいと思ってしまうのだが・・・