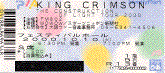この日、筆者は非常に複雑な思いで会場に向かった。
まさかBill BrufordのいないKing Crimsonを見る日が来ることになるとは・・・が、考えてみれば、「あの」渡り鳥ドラマーが、今まで脱退せずに何回もの再結成・活動停止に付き合ってきたこと自体が奇跡であったというべきなのだろう。それだけ、King Crimsonは、彼にとって新しい何かを得られる魅力的な活動であった、ということだ。
では、Billが脱退した今回のKing Crimsonは、もはや新しくないのか?魅力的でないのか?
ステージは非常にシンプルで、機材以外には背景に白無地の垂れ幕が貼ってあるのみ。これにさまざまなライトを当てたり、映像を映したりする。
午後7時。ほぼ定刻通り(こういうことは滅多になく、その意味で彼らは実に物堅い)に始まった。
曲は「VROOOM」。ほぼ満員の会場から大きな歓声・・・だが、Robert Frippのギターの音がまったく出てこない。苛立つFripp、苦笑いのAdrian Belew、動揺するTrey Gunn。いきなり波乱のスタートである。クルーが何やら配線をチェックし、やっと音が出た。だが、まだ時々途切れたりする。バランスが悪い。そのまま間奏のアルペジオに。やはり音が出てこない。とその時、ソロを弾いていたTrey Gunnのベースから突拍子もない音程の音符が飛び出してきた。ちょんぼである(笑)。よりによって、自分の最大の見せ場でミスるとは・・・動揺は広がる一方である。これがあの鉄壁のアンサンブルを誇るKing Crimsonかと疑いたくなるくらい無残なオープニングだったが、途中から完全に音が出てきたので、皆安心したのか、その後は無難にまとまった。2曲目の 「Thela Hun Ginjeet」で完全復活したあたりはさすが。
80年代Crimsonの曲は、もともと今回同様4人構成で演奏されていた曲だ。しかも、今回はドラムのPat MastelottoがRolandのエレクトリックドラムでフルセットを組んでいるから、当時の Bill BrufordがSimmonsのドラムを使っていたのと、まったく同じ状況なのである。したがって、前回の来日時のようにへヴィではなく、オリジナルに近い雰囲気が出ていたのは、当然といえよう。
Pat Mastelottoは非常に頑張っていた。前回はドラムが二人いて、しかも相手が縦横無尽に(無節操に)叩きまくるBillだったから、すっかり脇役に回っていた感があったが、今年はやっとスポットの当たる地位を手に入れたようだ。実際、技術的には非常に高いものを持っている人なのである。
同じことがTrey Gunnにもいえる。Tony Levinのスキンヘッド、どこか愛嬌のあるパフォーマンスと多彩な技に割を食っていたが、今回は地道な努力が報われたといったところか。
だが、華がない。今回の主役はまぎれもなくRobert Frippであり、相変わらずの超絶技巧ソロを弾いてはいたが、この人はスポットライトが嫌いらしく、いつも闇に包まれて演奏している(笑)。しかも、ご存知の通り椅子に座って引き続けるため、アクションは全くない。Adrian Belewは、象の鳴き声をギターで弾いてみせたり(今回はエフェクトを変えたのか、風邪を引いたような象の鳴き声だったが)、アンコールではアコースティック1本、たった一人で「Three of a Perfect Pair」を演奏したり、大いに楽しませてくれたが、類い稀なルックスが邪魔をしているためか(失礼!)、主役にはどうしてもなれない。あとの二人は、堅実にまじめなプレイをするのだが、どうしても優等生的な印象を払拭できない。
今回のライブを観て、あらためてKing Crimsonの華はBillとTonyだったのだ、と確信した。あの二人のプレイには技術以上の何かがあった。どんなリズムを繰り出してくるか、手に汗を握って待つという期待感があった。そして、一挙手一投足に、他の者では真似できないかっこよさがあった。(このかっこよさは、ロックでは重要な要素なのだ)
つまり、野球にたとえれば、3番、4番がBillとTonyで、派手な一発をかましてくれる役である。Robertはキャッチャー的存在で、チームの精神的リーダー、Adrianはトップバッターで、盗塁やら何やらを器用にこなす。Treyは2番、Patは6番で意外性を持つ、といったところだろうか。そんな感じなのである。
大砲が抜けたCrimsonだが、決してつまらなかったわけではない。オープニングを除いては演奏は完璧だったし、何よりも楽しそうであった。あんなに楽しそうに、にこやかにやっているRobertを見るのは初めてだ。聴く人にも修業・鍛練を要求した、かつての緊張感こそなかったが、メンバーの雰囲気がこちらにも伝わってきて、意外にも「楽しい King Crimsonのライブ」だった。筆者も十分に楽しむことができた。
結局70年代の曲は「Red」だけだったが、最も充実した演奏は、新譜からの曲でみられた。特に、「Larks' Tongues in Aspic Part IV」は出色の出来で、鳥肌ものであった。
そして、アンコールラストは、なんとDavid Bowieの「Heroes」だったのだ!
この事実に今回のすべてが凝縮されていると言ってよいだろう。確かにRobertは、この曲にギターとしてゲスト出演しているし、AdrianはDavid Bowieのツアーメンバーだったこともある。しかし、この選曲の柔軟さは驚きである。
結論:現在のKing Crimsonは、斬新ではないがハイ・クォリティかつ魅力的である。
最後に、観客についてだが、例によって年齢層は非常に高かった。皆しっかり予習をしてきたようで、イントロを少し聴いただけで、何の曲かわかってしまう(笑)。当然のように、David Bowieの曲にも反応していた。
先年、Paul GilbertがアンコールでEL&Pの「悪の教典」をやったとき、またはPlant & Pageがメドレーの中に The Doorsの「Break On Through」をやったときに、筆者の周囲では筆者以外、誰も反応できず、皆地蔵のように固まっていたことを思うと、プログレファンは恐ろしい、もとい、すばらしい。
次回はいつになるのだろうか・・・また、数年間活動が止まるのだろうか?噂によれば、「Larks' Tongues in Aspic Part V」が既に完成しているらしいが。